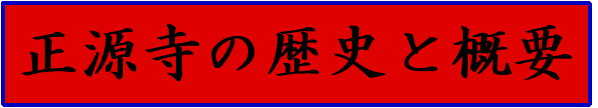 |
久留里 正源寺
正源寺の歴史と概要
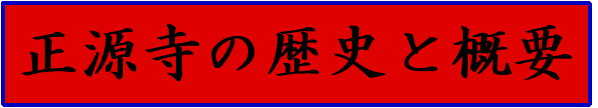 |
| 所在地 | 千葉県君津市久留里市場185-1 |  |
||
| 名称 | 福徳山 東陽院 正源寺 (ふくとくさん とうよういん しょうげんじ) |
|||
| 宗派 | 浄土宗 | |||
| 御本尊 | 阿弥陀如来坐像 |
| 当寺は、鎌倉時代の徳治2年(西暦1307年)時宗の高僧 他阿真教上人により、上総の念仏根本道場として創建されました。 他阿上人は、数年間この地に留まり、民衆にとけ込み踊り念仏によって布教に努められました。 その道場は、厳しい生活を強いられた民衆にとってはこの世の極楽浄土さながらに、明るく楽しい踊り念仏であふれていたと伝えられます。 それまで、安万支(アマキ)の里と言われていた当地は、生き仏様が久しく留まられた里ということで、久留里(クルリ)と呼ばれるようになったといいます。 その後二百年ほどたった天文15年(西暦1546年)、久留里城を本城として房総半島に一大勢力を築いた戦国大名 里見義堯(サトミ ヨシタカ)公にとりたてられて義堯公母君の菩提寺となりました。 その時当寺は、義堯公より260石の寄進を請け、母君の菩提の為にと阿弥陀如来を本尊として迎え、宗派を浄土宗に改めて、それまで特別の名称を持たなかった念仏道場を「福徳山 東陽院 正源寺」(フクトクサン トウヨウイン ショウゲンジ)と号する、塔頭4軒末寺8寺を有し、朝な夕なの念仏の声は町はずれまで響き渡ると言われた大寺院へと変貌していったのです。 また義堯公は、鎌倉北条氏との戦勝御礼として、境内に一つの堂を建立し、久留里城内に安置していた里見家代々の戦勝祈願仏であった観音像を「加勢観世音菩薩」と呼んで安置し、庶民の信仰をあつめました。 |
 |
 |
 |
||
| 往時の面影を残す、山門 | 本堂内陣 | 南房総最古といわれるイチョウの木 |
| 戦国時代も終わり、徳川政権の時代になると、久留里を追われた里見家は、南総館山から今の島根県へと任地替えとなり、ついには滅びることとなります。(この時の哀れな悲しい話を題材にして出来たのが「南総里見八犬伝」だそうです。) しかし、当寺は徳川幕府直轄の御朱印寺となり、里見家の丸二引の紋から徳川家の三つ葉葵の紋に付け替えられ、里見家代々の位牌は徳川家代々の位牌に取り替えられるという、里見色を全て排した寺院となっていきました。 今に残る里見家の面影は、里見家代々の必勝祈願佛「加勢観音」を安置する、観音堂だけとなっております。 栄枯盛衰は世の習い。徳川政権が終わりを告げ、新政権の下での明治時代になると、廃仏毀釈の嵐が吹き荒れ、それとともに葵の御紋の権勢と後ろ盾を失った当寺は、塔頭末寺すべてが焼失あるいは荒れ果てて廃寺となっていきました。 本坊 東陽院も昔日の大伽藍は焼失し、今に残る当時の面影は、山門の一部と樹齢700年を越す大イチョウのみとなりました。しかし、明治・大正・昭和の激動の時代を、歴代の住職並びに檀信徒が力を合わせて復興の努力がなされ、再び民衆のための本来の寺院として、生まれ変わったのです。 |
 |
 |
 |
 |